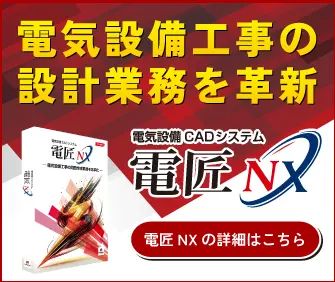建設業も対応必須!?電子帳簿保存法とは

2023年から導入される予定の仕入税額控除の新方式である「インボイス制度」で義務付けられているインボイスの適正保存に伴い、電子データでインボイスの受け渡しを採用する場合は、「電子帳簿保存法」という法律に則って適切に取り扱わなければなりません。この法律では、電子データの保存方法や対応書類などが細かく指定されているので、国税関係の帳簿や書類を扱う企業は必ず知っておくべきことでしょう。
そこで今回は、国税関係書類の取り扱いに欠かせない電子帳簿保存法について、詳しくご紹介いたします。
そこで今回は、国税関係書類の取り扱いに欠かせない電子帳簿保存法について、詳しくご紹介いたします。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類・帳簿、請求書、領収書、などを電子データとして保存できることを定めた法律です。 本来は、これらの税務関係書類を紙で保存されることが義務付けられていたものの、近年のテレワーク普及による紙業務の非効率が露呈してきたことなどを背景に、令和3年から4年にかけてデータ取り扱いや、保存に関する抜本的な見直しが行われました。それにより実施されたのが、この電子帳簿保存法です。また、電子帳簿保存法によりペーパーレス化が推進され、インターネットを介して取引を行っている多くの事業者が行ってきた電子取引においても、取引情報を紙に出力したり、保存したりすることができなくなりました。
さらに、今後この法律はすべての事業者を対象にする動向があるので、たとえインターネットでの取引を行っていなくても税務関係の書類や帳簿保存が発生する限りは、全ての企業・事業者において関連性の高い法律になっていくでしょう。ちなみに、電子帳簿保存法が対象としているものは、国税関係書類、国税関係帳簿、電子取引の3つの区分に分かれています。
さらに、今後この法律はすべての事業者を対象にする動向があるので、たとえインターネットでの取引を行っていなくても税務関係の書類や帳簿保存が発生する限りは、全ての企業・事業者において関連性の高い法律になっていくでしょう。ちなみに、電子帳簿保存法が対象としているものは、国税関係書類、国税関係帳簿、電子取引の3つの区分に分かれています。
電子帳簿保存の対象となる書類
ここでは、電子帳簿保存法の3つの区分について、詳しくご紹介させていただきます。対象書類の詳細は、以下の通りです。
<国税関係書類>
・賃貸対照表や棚卸表などの決算関係書類
・自己発行(請求書や見積書の控えなど)
・相手先からの受領(請求書、見積書など)を含む取引関係書類
<国税関係帳簿>
・仕訳帳
・売掛帳
・現金出納帳
・総勘定元帳
・固定資産台帳
<電子取引(電子メール・クラウドサービス・ EDI等)>
・請求書
・納品書
・領収書
・見積書
・注文書
業務上、上記の書類はさまざまな取引先とのやり取りで発生するものですが、電子帳簿保存法により過去に紙でやり取りしていた書類の管理方法の見直しなども必要になります。したがって、どの書類が該当するのか、またどの保存措置が必要となるのかを分別・整理していかなければなりません。
<国税関係書類>
・賃貸対照表や棚卸表などの決算関係書類
・自己発行(請求書や見積書の控えなど)
・相手先からの受領(請求書、見積書など)を含む取引関係書類
<国税関係帳簿>
・仕訳帳
・売掛帳
・現金出納帳
・総勘定元帳
・固定資産台帳
<電子取引(電子メール・クラウドサービス・ EDI等)>
・請求書
・納品書
・領収書
・見積書
・注文書
業務上、上記の書類はさまざまな取引先とのやり取りで発生するものですが、電子帳簿保存法により過去に紙でやり取りしていた書類の管理方法の見直しなども必要になります。したがって、どの書類が該当するのか、またどの保存措置が必要となるのかを分別・整理していかなければなりません。
電子データで保存するときの要件
実際に電子データで保存するときは、可視性(目で見えること)と、真実性(絶対的な正確さ)をベースにした、いくつかの要件があります。可視性においては、帳簿内容を主要な記録項目から検索することができる、日付と金額の検索を範囲指定で行える、2つ以上の条件による検索が行える、データ保存を行う場所にOSの入った電子計算機やプリンタ、ディスプレイが備え付けられており、迅速に出力作業を行えること、などが要件として定められています。また、真実性においては訂正や削除をした際にその内容を確認できる、業務処理期間を経過した後に入力したものの履歴が確認できる、電子データ作成に利用したシステムの仕様書や概要書、操作説明書が備え付けられている、データ保存を行う場所への電子計算機やプリンタ、ディスプレイの備え付け及び、迅速な出力作業を行えること、などが要件です。電子データで関連書類を保存する際には、上記の真実性のシステムに関する要件や可視性のほとんどの要件を満たすことが必須となります。なお、関連書類をスキャナで保存する際は、方式や所定日数などの多くの要件が定められているため、以下の国税庁ホームページよりご確認ください。
●国税庁HP https://www.nta.go.jp/index.htm
●国税庁HP https://www.nta.go.jp/index.htm
電子帳簿保存法を適用することのメリット
電子帳簿保存法には要件や確認すべき点が多く、面倒に感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、この法律の適用によってもたらされるメリットは多くあります。例えば、7年~10年の保存義務がある取引記録などの国税帳簿書類は、紙書類だとバインダーやファイルに綴じて保管することが多いので、スペースが必要な上に、長い保存期間の中で年々その量が膨大になっていきます。これを電子データ化することによって、パソコンやシステム内で保存できるようになるため、省スペース化を実現できるといえるでしょう。
また、データを探す際に古い紙データだと、保管場所から探し出す手間がかかりますが電子データであれば、検索機能ですぐに探し出すことができます。さらにID・パスワード管理やデータ閲覧制限の設定によって、データ自体の盗難防止や紛失防止においても効果を期待できるでしょう。なお、電子データ保存にすれば紙帳簿で必要な印刷用のインク、保存用のファイルやキャビネットなどを購入する必要がなくなるので、コストも削減できます。さらに、企業でのペーパーレス推進によって、紙資源の節約といったエコ活動を行えるメリットもあるでしょう。電子帳簿保存法には対処すべき点が多いとはいえ、電子化を導入するメリットも多くあるため、ぜひ積極的に導入を進めてみてください。
また、データを探す際に古い紙データだと、保管場所から探し出す手間がかかりますが電子データであれば、検索機能ですぐに探し出すことができます。さらにID・パスワード管理やデータ閲覧制限の設定によって、データ自体の盗難防止や紛失防止においても効果を期待できるでしょう。なお、電子データ保存にすれば紙帳簿で必要な印刷用のインク、保存用のファイルやキャビネットなどを購入する必要がなくなるので、コストも削減できます。さらに、企業でのペーパーレス推進によって、紙資源の節約といったエコ活動を行えるメリットもあるでしょう。電子帳簿保存法には対処すべき点が多いとはいえ、電子化を導入するメリットも多くあるため、ぜひ積極的に導入を進めてみてください。
猶予期間が終わる前に電子化への対応を
電子帳簿保存法は、2022年1月に施行されましたが、準備期間が短いことから過去2021年に公表された令和4年度税制改正大綱の中にある、電子取引における電子保存の義務化によって、電子帳簿保存法への順応に2年間(2022年1月〜2023年12月末まで)の猶予期間を認めることが定められました。とはいえ、実際に電子データ保存を進めるにあたってシステムの導入を行う場合は、事前準備やシステム選びに時間がかかり、インボイス制度への順応なども並行して行わなければなりません。そのような背景から実質的にはあまり猶予がないとも考えられるため、早めの運用見直しと、対応への計画・着手が必要になるでしょう。ただし、これらの対処に関して所轄の税務署長に申請する必要はないため、自社でシステムの導入を積極的に進めながら、電子帳簿保存法やペーパーレス化に早期に対応することがポイントになります。