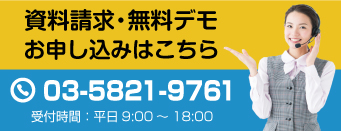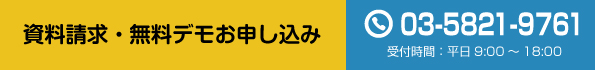SFAを導入する目的とは?営業活動効率化のために押さえておきたいこと
営業活動は究極のコミュニケーション活動だと考えています。個人のスキルに依存し、理屈では割り切れない感情が入り込んでくることもあるため、営業は属人的になりがちだと言われます。 属人的な営業もそれはそれで良いところはたくさんあるのですが、 ノウハウや情報が共有されにくい点があるもの事実です。
SFA(営業支援システム)はこうした属人的な営業に頼るのではなく、誰もが同じ営業活動を行えるよう平準化を目的としたシステムですが、導入の目的を何ももたずに使うと失敗しやすいシステム でもあります。
ここでは、SFAを導入にするあたり、どのような目的意識をもって導入に臨んだら良いかについてご紹介します。

SFA導入の目的を明確にする理由は?
SFAには多くのメリットがある一方、導入する際はその「目的」を明確化しておかなければ有効活用できない可能性があります。SFA導入の目的を明確にする理由は、次のとおりです。
導入自体が目的になってしまうから
SFAは営業活動を効率化し、目的を達成するためのツールです。しかし、検討を重ねるうちに、いつの間にか導入そのものが目的になってしまうケースがあります。導入の前には、 まず目的を明確にしましょう。たとえば、「顧客情報を一元管理し、商談に最適なタイミングを可視化する」、「見込み客の優先順位を明確化し、営業効率を高める」などです。 目的が定まったら、チーム全体でしっかりと共有しましょう。
現場スタッフの不満につながるから
SFAを利用し始めると、現場スタッフの作業量は増加したように感じられます。導入目的を明確にしておかなければ、現場スタッフは負担がただ増えただけと感じ、不満につながる可能性が高いです。 すると、本来は業務の効率化に役立つはずのSFAのメリットを現場が実感できない恐れもあります。またSFAにはさまざまな機能がありますが、必要な機能は自社の状況によって異なります。 導入する目的がしっかりと定まっていれば、不必要な機能を利用する必要がなくなり、現場スタッフの負担を軽減できるでしょう。
SFAの効果を発揮できないから
SFAが効果を発揮するためには、現場スタッフが営業活動を日々入力し、情報をリアルタイムに更新する必要があります。SFAが現場に定着せず、データが古いままだと、正しい分析を行えません。 導入の目的がしっかりと定まれば、日々の業務へどのように落とし込むべきかを設定できるようになります。入力のタイミングや担当者が明確になれば、入力漏れが予防でき、効果を十分に発揮できるでしょう。
SFAを導入する主な目的
「営業とは、モノを売るのではなく、人を売るのだ!」と新人のころ営業について、上司や先輩からこのように薫陶を受けた方は少なくないものと思います。モノを売るまえに、お客様から好感を持たれ、 信頼される人間たらんということを意味しており、今の世においても営業の基本であることに変わりはありません。裏を返せば、いくら商品が魅力的で、適正な価格であったとしても、それを売る営業の 人間性が信用できなければ、お客様はその商品を買ってはくれないということなのです。
“相手の懐に飛び込む”という言葉がありますが、優秀な営業ほど、相手の懐に飛び込むのが上手で、 結果、お客様の信頼を勝ち得て、売上目標を達成できているのでしょう。
しかしすべての営業がこのようであれば、その会社の業績は常に右肩上がりなのですが、現実はそうではありません。 特に経験の浅い営業が多い会社ではなおさらのことです。
従来、営業は商品の良し悪し以前に、営業の素質に依存する部分が多かったため、お客様から信頼の厚い営業が多くいる間は業績が良いのですが、 転職などで離職してしまった場合、逆に営業成績が落ちてしまったということも珍しくありません。つまり、人に依存する営業のやり方では、安定した売り上げの確保は難しくなっているのです。
属人化しやすい営業活動の効率化
以上のことから今までの営業活動は人に依存する部分が多いため、その実態を可視化することは難しいと言われていました。しかし、近年のITの進歩とSFAの登場により、そのデータを活用することで、 案件の属人化を解消できるようになったのです。 SFAの活用により、営業活動で得た情報の記録や管理を行うことができ、過去の商談履歴の閲覧、共有ができるようになりました。それにより今まで ボトルネックになっている部分もあぶり出すことができるようになりました。案件がクローズできない原因の見える化で、具体的な対応策を考えることができるようになったのです。
営業担当ごとの進捗状況を可視化
SFAを使うことにより、営業の進捗、商談内容、今後の営業活動内容を集約し、蓄積できるようになります。 結果、商談のステータスや提案内容を可視化できるだけでなく、管理者が各営業担当者の活動を把握 できるため、正当な評価ができるようになります。営業成績が優秀な者と売り上げが伸び悩んでいる担当者のデータを比較できるため、原因の特定、改善策の提案などが可能となります。
ノウハウや資料の共有
SFAの活用は、営業の活動内容の把握や商談、案件のプロセス管理だけではありません。いままで個々の営業が蓄積してきた経験やノウハウ、資料の共有が安易にできるようになることです。
特に、新人営業が不得手とする新規営業先へのアプローチ方法や訪問先でのヒアリング内容などを共有できることは伸び悩んでいる営業の成長に大きく貢献するものとなるでしょう。 SFAでは、個々の営業が作成した顧客むけの提案資料を保存できるため、わざわざ共有する手間が省けるだけでなく、教育コストの軽減につながります。業務に必要な資料の管理を一元化できるのも、 SFA活用のメリットと言えます。
営業活動や案件の管理
SFAの導入によって案件の基本情報と受注のための情報を紐づけることができるようになります。基本情報とは、商談日や取引先の事業内容、担当者の部署名、タイトル、名前などで、受注のための情報 とは商談の進捗状況、見込み度、受注予定日、売上予測額 などを指します。このような情報はこれまでExcelや日報の形で管理していたのですが、大抵は各営業のパソコンに分散していました。 SFAではこれらの情報を一元化できるため、確認したいときに案件ごとの情報や進捗を素早く把握できるようになるのです。
SFAの導入目的を明確化し、最適なツールを選ぶ方法
営業部門が抱える課題を明らかにする
どのようなシステムにしても、採用にあたってはその目的を明確にしなくてはなりません。世の中で、いくらSFAやCRMが流行っていても、SFA、CRM導入ありきでは必ずといってよいほど失敗してしまいます。 そのためには、自社が抱えている問題や課題を客観的に挙げてみて、分析することから始めなくてはなりません。
「担当者によって売り上げに差がある」「情報共有を効率よく行えない」「当月の売上見込みが 立ちにくい」など、現状の課題を挙げることで、何を改善するべきか、何を共有すべきかを営業部門のメンバー全体で明確にする必要があります。
明確になった課題に対して、SFAのどのような機能を活用できれば、 その課題を解決できるのかを十分に検討することです。自社のことはなかなか客観的に分析することができない場合は、中小企業診断士など外部のコンサルタントにも参加してもらい、外部の立場から課題を分析 してもらう方法もあります。
SFAの具体的な機能や役割を把握する
SFA導入を検討する際、必ずいってよいほど引き合いに出されるのがCRMです。「わが社にとってはSFAよりもCRMが必要だ!」という声です。気を付けないといけないのは、本来SFAを導入すべきところ、 声の大きいほうに引っ張られて、ついCRMを導入してしまうということです。
SFAの導入検討時にかならず引き合いに出てくるCRMとSFAは何が異なるのでしょうか?SFAは営業の行動を管理し、 それを日報という形で可視化します。日報には時系列での営業の活動内容が記載されているだけでなく、商談情報が明記されています。いわゆる案件と呼ばれるものです。案件の内訳として売上予測金額、 時期、商品内容、数量、見込み度などがあります。その案件の進み具合をSFAではプロセスとして管理します。つまりSFAは社内に向けたサービスであり、内向きのシステムなのです。
一方、CRMは顧客との 関係を深めることを目的としたシステムです。テレビや新聞、雑誌を使ったキャンペーンなどのマスマーケティングではなく、顧客ごとにサービスを提供するOne to Oneマーケティングの ためのシステムとなります。ですから、顧客ごとのプロファイルはもちろん、購買履歴やユニークなメールマガジンの配信など、その人のためだけのマーケティングを行うことを目的としたシステムがCRMと なります。顧客にむけたサービスですから、SFAとは反対の外向きのシステムとなります。ただ、SFAもCRMも顧客マスターあるいは顧客データベースと呼ばれる顧客リストを最初に構築することから、 その違いが理解されにくい点があることは確かです。
したがって、社内にむけたサービスであるSFAの機能には、一般的に営業報告作成機能、案件管理機能、商談プロセスの管理機能、商談履歴の記録機能が あります。これら機能が現場の営業にとって使いやいものかどうかを十分に検討する必要があります。
必要な機能があるか
SFAツールはさまざまな種類があるため、必ずしも自社の課題に対して適切な機能を備えているとは限りません。たとえば「営業ごとの売上数値の差が大きい」、「チームの売上金額が安定しない」といった課題がある場合、 それらを解消する機能に秀でたシステムを選ぶ必要があります。また、機能が多すぎるツールを選ぶと現場スタッフが使いこなせず、コストだけがかかってしまう可能性もあります。導入する前に、どのような機能が必要か しっかりと検討しましょう。
操作性を確認する
SFAを選ぶときは、操作性がよいことも重要なポイントです。報告ごとに同じ内容を何度も入力する必要のあるものや、顧客情報の手入力が多いシステムでは作業負担が大きく、SFAの定着は進まないでしょう。 組織全体のパフォーマンスを低下させる恐れもあるため、SFAの操作性の高さは重要なポイントとなります。操作性を確かめるためには、実際にシステムに触れることが大切です。本格的に導入する前に、 無料トライアルを試せるSFAツールを選ぶとよいでしょう。
モバイル対応しているか
外回りが多い営業にとって、オフィス外からもSFAを利用できるかどうかは大切なポイントです。スマートフォンやタブレットからも利用できるツールを選べば、隙間時間を有効活用できるほか 、商談中にSFAにアクセスして必要な情報をスピーディーに確認できます。またスマホに対応していれば、商談終了後に帰社してデータを入力する必要がありません。業務効率が向上するほか、 コストの削減にもつながるでしょう。
既存ツールとの連携が可能か
SFA以外に自社で運用しているシステムがすでにある場合は、既存システムと連携できるかも重要なポイントです。連携がとれないSFAを導入してしまうと、既存システムのデータを新たにSFAへ 入力しなおす手間が発生してしまいます。既存のツールと連携ができれば、データの一元管理や業務効率の向上につながります。スケジュール管理ツールや経理システムなどの自社のツールと、 導入予定のSFAが連携できるか、事前にしっかりとチェックしておきましょう。
SFAを導入する際の注意点
ここでは、SFAを導入する際の注意点を4つご紹介いたします。
導入後、効果が出るまでは時間がかかる
どのようなシステムでも、導入したからといってすぐに効果が現れるとは限りません。SFAも導入後、すぐに期待していた効果が出るわけではないとおもったほうが良いでしょう。 そのためには、継続的な利用が重要であり、そのためには社員が続けて活用できるように、いきなりすべての機能を使うのではなく、初めのうちは使用できる機能を制限しても良いと思います。 慣れてきたら、徐々にほかの機能も使えるようにすれば良いのです。そうすれば、早くて半年、あるいは1年もすれば、営業も操作に慣れてきて、もうSFA抜きでは営業活動ができなくなるかと思います。
管理することが目的にならないよう注意する
SFAを導入後、効果がでるまで継続的な運用が必要だと述べましたが、使用していくうちに、ツールを使いこなすことや管理することが目的にすり替わってしまいがちに なることがあります。SFA導入の最大の目的は、営業が作り出す商談や案件をすべてクロージングし、最大限の売上を確保することにあります。
ところが、いつの間にか SFAを使うことや管理することが目的になってしまうことがあります。こうしたことを防ぐために、SFA導入の目的は何なのかを企業のトップだけが理解するのではなく、 マネージャークラスはもちろんすべての営業メンバーにいたるまですべての社員に伝え、理解してもらうことが大切です。
さらに目的が異なったしまうことと同じくらい 陥りやすいのが、収集したデータの分析です。営業が足を棒にして集めてきた貴重な商談情報や顧客情報、競合情報などを分析しないままにして、次の商品開発やマーケ ティング活動へと活用できずに終わってしまうことがあります。これではせっかくのSFAが宝の持ち腐れとなってしまいます。
日々の情報入力が負担にならないようにする
SFA導入初期にありがちなのが、早期に効果を上げようとして、操作に不慣れな営業に負担をかけてしますことがあります。特に慣れない 入力作業に営業たちの工数がかかりすぎると、敬遠して継続的に使用してもらえなくなることがあります。ですから、自社にとって不要な 項目はカットし、入力しなくても良い状態にします。さらに定期的に営業からフィードバックをもらうようにし、その結果から不要な機能や 不便な部分が見えてきます。これによりSFAの内容を見直して、自社にあったSFA環境を作り上げていくのです。
お試し利用で自社に合ったSFAを見つける
ネット検索で、SFAと入力するといくつものSFAが検索できます。各社各様、いろいろな特徴をもっていますので、一概に優劣はつけられません。 大事なのは、自社の課題を解決してくれるSFAであるかどうかということです。ですから高機能=良いSFAではないのです。
そこで、失敗しない ためにも、3社くらいのSFAをお試し利用することをお勧めします。今のSFAやCRMのサービスはクラウド環境で提供されることがほとんどですから、 無料で1か月間お試し利用することができるのです。まずは、自社の課題を詳らかにし、それら課題を解決してくれるSFAはどのようなものがあるのか、 お試し利用を活用しながら検討してみてください。
まとめ
SFAの導入にあたり、目的の明確化が成功のカギとなります。営業活動の効率化や情報の管理・共有など、自社の課題に合わせた目的を定めたうえで SFAを有効活用しましょう。SFA・営業支援システム「NICE営業物語 on kintone」は、顧客管理機能や案件管理、商談プロセス管理といった便利な 機能などを備えており、適切な情報管理やメンバー間での情報共有に役立ちます。どこからでも営業報告が可能なクラウドサービスで、APIによるシステム 連携にも対応しています。30日間の無料体験も行っているため、実際に導入したケースを想定しながら使用感を確認できます。どこからでも利用でき、 操作性の高いSFAを導入したいとお考えの場合は、ぜひご検討ください。