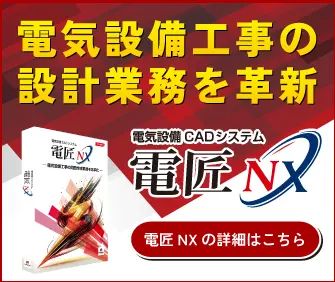電気工事業で満たさなければならない建設業許可の要件とは

電気工事業を含む建設業界で規模の大きな施工を受注する際は、建設業法に則り建設業許可を取得する必要があります。また、電気工事業務に関する法律に従う必要がある場合には、電気工事の金額や取り扱う電気工作物によって、電気工事業向けの建設業許可の登録手続きを別途各都道府県知事や経済産業大臣へ行わなければなりません。つまり、単純に建設業許可を取得するだけでは、電気工事業界で独立できない可能性もあるということです。
そこで今回は、今後独立や開業を検討されている方々に向けて、電気工事業で満たさなければならない建設業許可の要件について、詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧いただき、電気工事業界で独立開業を行う際の手続きの参考にしてください。
そこで今回は、今後独立や開業を検討されている方々に向けて、電気工事業で満たさなければならない建設業許可の要件について、詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧いただき、電気工事業界で独立開業を行う際の手続きの参考にしてください。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業者として500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の規模の工事を受注する場合、必ず事前に取得しておかなければならない許可のことです。これは建設業の適正化を目的に制定された、建設業法に基づいたものであり、日本国内のすべての建設業者・建設会社・個人事業者が対象となります。
しかし、中には軽微な工事を受注する場合など一部の例外も存在しており、その例外に当てはまる場合などは、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。とはいえ、大規模な工事の受注なども視野に入れて会社を設立する場合は、建設業許可を取得する方が良いため、今後独立をお考えの方は何らかの許可を取る必要があるということを念頭に入れておくべきでしょう。
また、電気工事業の建設業許可を取得する場合、変電・発電設備、構内の電気設備、送配用電気設備など、さまざまな電気設備の設置工事が対象となります。軽微な工事として許可取得が必要にならない場合もありますが、その場合でも電気工事である限りは別途、電気工事業者登録を取得しなければならないことを覚えておきましょう。なお、建設業許可と電気工事業者登録は要件や手続き方法がそれぞれ異なるため、詳細については各自治体の窓口にお問い合わせください。
しかし、中には軽微な工事を受注する場合など一部の例外も存在しており、その例外に当てはまる場合などは、必ずしも建設業許可を取得する必要はありません。とはいえ、大規模な工事の受注なども視野に入れて会社を設立する場合は、建設業許可を取得する方が良いため、今後独立をお考えの方は何らかの許可を取る必要があるということを念頭に入れておくべきでしょう。
また、電気工事業の建設業許可を取得する場合、変電・発電設備、構内の電気設備、送配用電気設備など、さまざまな電気設備の設置工事が対象となります。軽微な工事として許可取得が必要にならない場合もありますが、その場合でも電気工事である限りは別途、電気工事業者登録を取得しなければならないことを覚えておきましょう。なお、建設業許可と電気工事業者登録は要件や手続き方法がそれぞれ異なるため、詳細については各自治体の窓口にお問い合わせください。
電気工事業に建設業許可が必要な理由
一定規模以上の電気工事を行う際に建設業許可の取得が必要な理由が気になる方も多いのではないでしょうか?実際のところ、電気工事業には他の建設業と同様に業務適正化を目的とした法律である、電気工事業法が定められています。業務適正化の内容を具体的に説明すると、手抜き工事や会社都合による、電気工事の失敗や取りやめを防ぐことで発注者を保護することが目的となっています。
建設業許可を取得することは、業務適正化を実現するための法律で定められているため、一定規模以上の電気工事を受注する場合は必ず取得しなければなりません。仮に建設業許可を取得せずに一定規模以上の電気工事を受注した場合は違反となり、懲役や罰金を科せられてしまいます。
また、一般建設業許可の対象となる幅広い電気工事は500万円という工事費用を基準としており、その金額によって工事内容が軽微であるか、もしくはそうでないかを判断するのが一般的です。加えて、500万円以上の電気工事の受注をする場合、電気工事業における一般建設業許可を受ける流れとはなりますが、仮に元請けとして受注する工事の発注金額が4000万円を超える場合は、この限りではありません。そのような場合、電気工事業の「特定建設業許可」という許可証も、併せて取得しておく必要があります。
幅広く電気工事を受注したいと考えている方は、まず一般建設業許可を取得することを義務として捉えた上で、お客様にご信頼いただける会社づくりを目指しましょう。
建設業許可を取得することは、業務適正化を実現するための法律で定められているため、一定規模以上の電気工事を受注する場合は必ず取得しなければなりません。仮に建設業許可を取得せずに一定規模以上の電気工事を受注した場合は違反となり、懲役や罰金を科せられてしまいます。
また、一般建設業許可の対象となる幅広い電気工事は500万円という工事費用を基準としており、その金額によって工事内容が軽微であるか、もしくはそうでないかを判断するのが一般的です。加えて、500万円以上の電気工事の受注をする場合、電気工事業における一般建設業許可を受ける流れとはなりますが、仮に元請けとして受注する工事の発注金額が4000万円を超える場合は、この限りではありません。そのような場合、電気工事業の「特定建設業許可」という許可証も、併せて取得しておく必要があります。
幅広く電気工事を受注したいと考えている方は、まず一般建設業許可を取得することを義務として捉えた上で、お客様にご信頼いただける会社づくりを目指しましょう。
電気工事業における建設業許可の要件
先述の通り、一定規模以上の電気工事を受注する場合は建設業許可等の取得が求められますが、許可を取得するためには一定の要件が定められています。建設業許可を取得するための具体的な要件は以下のような内容であるため、事前に確認しておきましょう。
1. 経営管理能力があること
2. 専任技術者がいること
3. 財産的基礎(財務力)があること
4. 業務への誠実性があること
5. 廃棄物処理法などの法の遵守をすること
6. 社会保険に加入していること
上記要件には、それぞれに細かな条件が定められているため、詳細は各自治体にご確認ください。 なお、専任技術者というのは第一種・第二種電気工事士や一級・二級電気工事施工管理技士などの、国家資格を所有していることに加えて、規程の業務経験を持っている方のことを指します。
1. 経営管理能力があること
2. 専任技術者がいること
3. 財産的基礎(財務力)があること
4. 業務への誠実性があること
5. 廃棄物処理法などの法の遵守をすること
6. 社会保険に加入していること
上記要件には、それぞれに細かな条件が定められているため、詳細は各自治体にご確認ください。 なお、専任技術者というのは第一種・第二種電気工事士や一級・二級電気工事施工管理技士などの、国家資格を所有していることに加えて、規程の業務経験を持っている方のことを指します。
建設業許可を得て質の高い電気工事業者を目指そう
建設業許可を取得することにより、事業者側が得られるメリットは複数あります。実務的に見ても、建設業許可がある業者や会社であれば、質の高い電気工事業者として認知されるでしょう。建設業許可を取得しているということは顧客への信用力に直結するため、規模の大きな工事や公共工事の受注機会が増えたり、融資を受けやすくなったりするなど、経営や資金繰りの面でもメリットが多いです。
また、一般的に業務の範囲が幅広い電気工事では、建設業許可を取得していない場合でも従事できる作業があるものの、電気配線の接続や最終動作確認などは電気工事業法に基づく建設業許可がなければ行えません。そのため、建設業許可を取得していない場合、行えない作業のみを外注して他業者へ依頼しなければならず、一社で一貫した作業ができないということが弱みになってしまいます。お客様に安心して一貫したサービスをご提供するためにも、事前に電気工事における建設業許可に対する知識を深めておくことが大切です。
また、一般的に業務の範囲が幅広い電気工事では、建設業許可を取得していない場合でも従事できる作業があるものの、電気配線の接続や最終動作確認などは電気工事業法に基づく建設業許可がなければ行えません。そのため、建設業許可を取得していない場合、行えない作業のみを外注して他業者へ依頼しなければならず、一社で一貫した作業ができないということが弱みになってしまいます。お客様に安心して一貫したサービスをご提供するためにも、事前に電気工事における建設業許可に対する知識を深めておくことが大切です。
電気工事業者のさまざまな業務をサポートする「電匠NX」とは
電気工事業で独立される方の多くは大量の書類作業や事務作業に工数をとられるため、人手不足や作業効率の低下に悩まされているというケースが多いです。
そんな電気工事業者様が抱えるさまざまな業務をサポートするために開発された、電気工事専用のCADシステム、「電匠NX」 をご紹介させていただきます。電匠NXには、電気設備や電気工作物に関わる膨大な専門知識をインプットしており、電気図面などの作成業務を自動機能で行えるといった便利な機能が備わっています。電匠NXの機能を活用すれば、これまではエクセルや手書きで行っていた図面作成や電力会社に提出するための施工証明書、お客様向けの提案プランなどを、よりスムーズに作成することが可能です。
また、当システムはそれぞれ別の場所に所属している作業員が、同時に作業を行うこともできる仕様となっているため、図面作図の作業工数を複数人(最高3人まで※)で分散化することができます。さらに、データの互換性や対応可能なデータ形式の数にもこだわりながら、機能性・利便性の高さも追求しておりますので、ITに精通していない方やCADの操作に不慣れな方も簡単に操作いただけます。
充実したサポート機能を備えている電気工事専用CAD「電匠NX」の導入をお考えの方は、ぜひお気軽に資料請求をお求めください。
※1ライセンスで3人まで同時利用可能(スタンダード版のみ)
そんな電気工事業者様が抱えるさまざまな業務をサポートするために開発された、電気工事専用のCADシステム、「電匠NX」 をご紹介させていただきます。電匠NXには、電気設備や電気工作物に関わる膨大な専門知識をインプットしており、電気図面などの作成業務を自動機能で行えるといった便利な機能が備わっています。電匠NXの機能を活用すれば、これまではエクセルや手書きで行っていた図面作成や電力会社に提出するための施工証明書、お客様向けの提案プランなどを、よりスムーズに作成することが可能です。
また、当システムはそれぞれ別の場所に所属している作業員が、同時に作業を行うこともできる仕様となっているため、図面作図の作業工数を複数人(最高3人まで※)で分散化することができます。さらに、データの互換性や対応可能なデータ形式の数にもこだわりながら、機能性・利便性の高さも追求しておりますので、ITに精通していない方やCADの操作に不慣れな方も簡単に操作いただけます。
充実したサポート機能を備えている電気工事専用CAD「電匠NX」の導入をお考えの方は、ぜひお気軽に資料請求をお求めください。
※1ライセンスで3人まで同時利用可能(スタンダード版のみ)