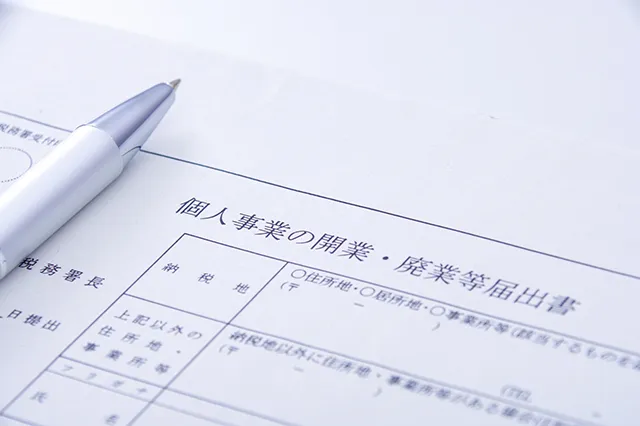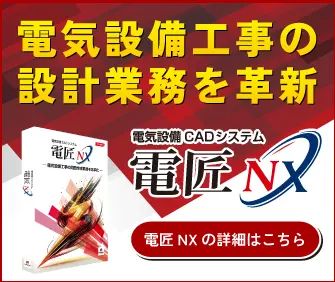プロとして知っておこう!電気工事で設置する電気設備の耐用年数

電気工事で設置する電気設備はそれぞれに耐用年数があり、その年数に至るまでトラブルなく正常に使い続けられる期間と思われがちですが、実際は設備そのものの資産価値が維持できる年数が法により定められています。特に住宅やビル、施設などには多種多様な電気設備が設置されているため、資産価値の維持が重要視されています。そのため、これらの設置工事やメンテナンスを行う際は耐用年数の知識を身につけておく必要があるといえるでしょう。
今回は、プロとして知っておきたい電気工事で設置する電気設備の耐用年数や概要、重要性を解説いたします。現役で電気工事士として電気設備工事の現場に従事されている方などは、ぜひ知識の再確認として参考にしていただければ幸いです。
今回は、プロとして知っておきたい電気工事で設置する電気設備の耐用年数や概要、重要性を解説いたします。現役で電気工事士として電気設備工事の現場に従事されている方などは、ぜひ知識の再確認として参考にしていただければ幸いです。
電気工事における電気設備の概要
電気設備は電気を発生させて、送ったり使用したりする設備を指します。つまり、電気の発電・送電、そして安定供給を行うための電気工作物から、実際に電気を人々が使用するための機器、通信設備、そして各施設に設置されている防犯・消防用設備など、社会の基盤として存在しているすべての設備が電気設備ということになります。
電気設備は、住宅だけでなく各施設や店舗、ビルなどのありとあらゆる建物の内外に付随しており、それらの建物を機能させるためになくてはならない存在です。また、発電会社が設置している設備の場合は、発電・送電設備、変電設備、配電設備、そして電気を使用するためのコンセントや照明器具などといった設備が代表的になるでしょう。
これらの電気設備が持つ最大の役割は、人々が快適に電気を利用できるようにすることであるため、社会における電気設備工事のニーズも非常に高いといえます。
電気設備は、住宅だけでなく各施設や店舗、ビルなどのありとあらゆる建物の内外に付随しており、それらの建物を機能させるためになくてはならない存在です。また、発電会社が設置している設備の場合は、発電・送電設備、変電設備、配電設備、そして電気を使用するためのコンセントや照明器具などといった設備が代表的になるでしょう。
これらの電気設備が持つ最大の役割は、人々が快適に電気を利用できるようにすることであるため、社会における電気設備工事のニーズも非常に高いといえます。
電気工事で設置される電気設備の耐用年数
電気工事で設置される電気設備は、法律に則りそれぞれに異なる耐用年数が定められていますが、代表的な例は以下のとおりです。
・発電設備の耐用年数
発電設備は、風力・太陽光発電システムなどに必要な電気を発生させる設備を指します。太陽光発電や風力発電のシステムは、電気業用及び金属製の設備に分類されるため、耐用年数は17年程に定められています。太陽光や風力以外にも水力発電やガスタービン発電がありますが、水力設備は20年〜22年、ガスタービン発電設備の耐用年数は15年程度です。
・構内電気設備の耐用年数
建物・施設内において送られてくる電気を利用するための電気設備が、構内電気設備です。これは、一般家庭をはじめとした店舗や工場で電気製品を使用する際などに必要な設備で、主に照明・電灯用設備、コンセント類が該当します。そして、これら構内電気設備に定められている耐用年数は15年間程ですが、蓄電池電源設備のみが例外として6年間となっています。
・送配電設備の耐用年数
送配電設備は、発電設備〜構内電気設備間で電力を送電するための設備のことで、主に電線がこれに該当します。電線は電気業用設備で耐用年数は15年〜22年、最長でも30年を経過すると漏電のリスクが高まるので注意が必要です。
なお、より一般の方々にとって身近な電気設備としてはパソコンや軽自動車が挙げられますが、これらの耐用年数は4年間程と短めです。
上記のように定められている耐用年数を経過すると、すぐに使用できなくなるわけではありませんが、故障やトラブルが起こりやすくなり、使用時にトラブルが発生する可能性があります。しかし、故障・トラブルが起こるタイミングやトラブルの程度は、電気設備の使用状況によって異なるため、メンテナンスや修繕を行う際は耐用年数にとらわれず、個々の状態を確認することが大切です。そのため、耐用年数を把握しながら経過年数も考慮した上で現状を確認し、それらに応じたメンテナンスを施すことがポイントになります。
・発電設備の耐用年数
発電設備は、風力・太陽光発電システムなどに必要な電気を発生させる設備を指します。太陽光発電や風力発電のシステムは、電気業用及び金属製の設備に分類されるため、耐用年数は17年程に定められています。太陽光や風力以外にも水力発電やガスタービン発電がありますが、水力設備は20年〜22年、ガスタービン発電設備の耐用年数は15年程度です。
・構内電気設備の耐用年数
建物・施設内において送られてくる電気を利用するための電気設備が、構内電気設備です。これは、一般家庭をはじめとした店舗や工場で電気製品を使用する際などに必要な設備で、主に照明・電灯用設備、コンセント類が該当します。そして、これら構内電気設備に定められている耐用年数は15年間程ですが、蓄電池電源設備のみが例外として6年間となっています。
・送配電設備の耐用年数
送配電設備は、発電設備〜構内電気設備間で電力を送電するための設備のことで、主に電線がこれに該当します。電線は電気業用設備で耐用年数は15年〜22年、最長でも30年を経過すると漏電のリスクが高まるので注意が必要です。
なお、より一般の方々にとって身近な電気設備としてはパソコンや軽自動車が挙げられますが、これらの耐用年数は4年間程と短めです。
上記のように定められている耐用年数を経過すると、すぐに使用できなくなるわけではありませんが、故障やトラブルが起こりやすくなり、使用時にトラブルが発生する可能性があります。しかし、故障・トラブルが起こるタイミングやトラブルの程度は、電気設備の使用状況によって異なるため、メンテナンスや修繕を行う際は耐用年数にとらわれず、個々の状態を確認することが大切です。そのため、耐用年数を把握しながら経過年数も考慮した上で現状を確認し、それらに応じたメンテナンスを施すことがポイントになります。
電気設備の耐用年数の重要性
電気設備の耐用年数は資産価値を把握できるだけでなく、安全性と動作確認をする上でも欠かせない要素です。万一耐用年数を経過しているにも関わらず電気設備を使用し続けていれば、本来あるはずの機能性を発揮できず、使い勝手が悪くなる場合もあります。また、動作が鈍くなったり使いづらくなったりするだけでなく、無駄な電力消費などの非効率化が起こる恐れもあり、余計なコストが発生します。
例えば、古い冷暖房設備をメンテナンスなしで使い続けている場合、室温の上げ下げが正常にできない、異音がするなどのトラブルが起こり、無理な稼働で電力を浪費してしまうケースがあるでしょう。他にも、電気設備の絶縁部品の劣化や浸水状態を放置していると、停電、漏電、感電などのリスクが高まり、最悪の場合は火災に繋がってしまう恐れもあります。
耐用年数に応じた定期的なメンテナンスや点検などの保安管理を行えば、こうしたリスクを予防することができますが、仮に保安管理をせずに事故が起きた場合、法に基づいて設置者の責任が追及されます。火災などの大きな事故が起きてしまった場合は、罰金を課せられることもあるということを覚えておきましょう。
例えば、古い冷暖房設備をメンテナンスなしで使い続けている場合、室温の上げ下げが正常にできない、異音がするなどのトラブルが起こり、無理な稼働で電力を浪費してしまうケースがあるでしょう。他にも、電気設備の絶縁部品の劣化や浸水状態を放置していると、停電、漏電、感電などのリスクが高まり、最悪の場合は火災に繋がってしまう恐れもあります。
耐用年数に応じた定期的なメンテナンスや点検などの保安管理を行えば、こうしたリスクを予防することができますが、仮に保安管理をせずに事故が起きた場合、法に基づいて設置者の責任が追及されます。火災などの大きな事故が起きてしまった場合は、罰金を課せられることもあるということを覚えておきましょう。
耐用年数を正しく把握して電気工事の質を高めよう
電気設備は家庭用や施設用に関わらず、どの設備も5年〜15年程の耐用年数が定められており、年数に応じた取り扱いやトラブルへの対処が必要です。もちろん、トラブルや故障の原因のすべてが耐用年数の経過とは言い切れませんが、不具合が起きやすくなる年数の目安にはなります。また、電気設備の耐用年数を経過してからの故障による事故があった場合は、店舗・オフィスの売り上げ減少や損害賠償にまで発展する恐れがあるでしょう。
そのため、耐用年数をしっかりと把握して耐用年数に合わせた定期的なメンテナンスや点検を行わなければなりません。定期的なメンテナンスを行っていれば、修理・交換によって設備の寿命を延ばしたり、トラブルを事前に避けたりすることで設備の安全性を保ち続けられるでしょう。電気設備を点検することは電気事業法でも定められており、電気設備を所持する方の義務でもあります。
また、電気設備工事は電気工事士や電気主任技術者などの専門的な知識を有する者が行う工事であり、特に事業用の電気工作物を設置する工事では電気主任事業者の配置が必須です。そのため、電気工事業者は電気主任技術者が必要な現場であると判断された場合に速やかに現地に人材を派遣できるよう、専門的な知識を有する人材を確保しておく必要があるといえるでしょう。
正確な耐用年数を把握した技術者が工事を行うとお客様からの信頼度を高めることに加えて、電気工事全体の質を向上させることができます。
そのため、耐用年数をしっかりと把握して耐用年数に合わせた定期的なメンテナンスや点検を行わなければなりません。定期的なメンテナンスを行っていれば、修理・交換によって設備の寿命を延ばしたり、トラブルを事前に避けたりすることで設備の安全性を保ち続けられるでしょう。電気設備を点検することは電気事業法でも定められており、電気設備を所持する方の義務でもあります。
また、電気設備工事は電気工事士や電気主任技術者などの専門的な知識を有する者が行う工事であり、特に事業用の電気工作物を設置する工事では電気主任事業者の配置が必須です。そのため、電気工事業者は電気主任技術者が必要な現場であると判断された場合に速やかに現地に人材を派遣できるよう、専門的な知識を有する人材を確保しておく必要があるといえるでしょう。
正確な耐用年数を把握した技術者が工事を行うとお客様からの信頼度を高めることに加えて、電気工事全体の質を向上させることができます。
電気工事専用CAD「電匠NX」で各種業務の効率をアップ!
耐用年数の経過や故障などによるメンテナンス工事の需要が高い背景などから、日々多忙な電気設備工事の業務効率UPを図りたい場合は、電気工事専用CADを導入をおすすめします。
システムズナカシマでは、長年培ってきた技術力と研究成果を生かし、電気設備工事に特化した電気工事専用CAD「電匠NX」を開発いたしました。電匠NXを導入いただければ、これまでは手書きやExcelなどで行っていた作図作業を短時間で進められることに加えて、より正確性の高い図面を完成させることができます。
特に作図における配線・配置・編集をスムーズに行える自動編集機能を活用すれば、作図に必要な工数を大幅に削減可能です。他にも、インターネット環境があれば1つのライセンスで3人まで使用可能、台数制限がなくインストール可能、などの便利なネットワークシステムを導入しておりますので、社内外で複数人同時にCADの作業を行うこともできます。
電気工事における図面作成業務の効率化を図りたい方は、ぜひ弊社の電匠NXについてお気軽に資料請求をお求めください。
システムズナカシマでは、長年培ってきた技術力と研究成果を生かし、電気設備工事に特化した電気工事専用CAD「電匠NX」を開発いたしました。電匠NXを導入いただければ、これまでは手書きやExcelなどで行っていた作図作業を短時間で進められることに加えて、より正確性の高い図面を完成させることができます。
特に作図における配線・配置・編集をスムーズに行える自動編集機能を活用すれば、作図に必要な工数を大幅に削減可能です。他にも、インターネット環境があれば1つのライセンスで3人まで使用可能、台数制限がなくインストール可能、などの便利なネットワークシステムを導入しておりますので、社内外で複数人同時にCADの作業を行うこともできます。
電気工事における図面作成業務の効率化を図りたい方は、ぜひ弊社の電匠NXについてお気軽に資料請求をお求めください。
#電気設備 #耐用年数