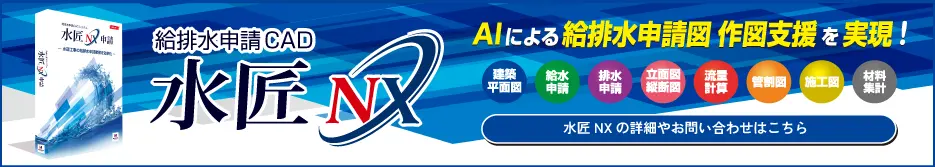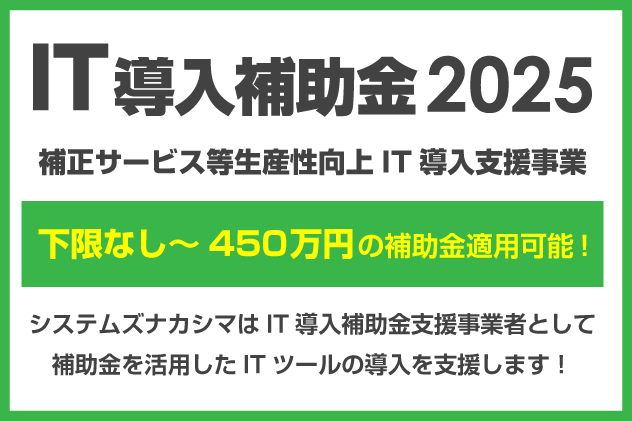【2025年予定】建設業法の改正について

建設業法は、建設業界において厳守しなければならない法律として設けられており、すべての建設業者がそれに則って活動しています。 建物やインフラの建設を行う建設業は、国の維持・発展の根幹を担う業種です。
そんな建設業界の品質向上・適正化を目的とした法律として 運用されてきた建設業法は、2025年に改正が予定されています。建設業法は非常に重要性の高い法律であり、その改正に際しては、 多くの建設業者が影響を受けることになるでしょう。そのため、法改正についてよく理解し、正しく対応することが重要です。
そこで、 この記事では2025年に予定されている建設業法の改正について、具体的な内容に触れながら、詳しくご紹介いたします。
2025年施行予定の建設業法等改正とは
2025年から施行される予定の建設業法は、2024年に国会で可決・成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」に 基づいています。改正法は、公布日から1年6カ月以内に完全施行される予定となっており、関連する業者はこれを念頭に置いて活動していかなければなりません。
今回の法改正の主な目的として、建設業界における労働者の処遇改善を掲げており、働き方改革を視野に入れたものとなっています。建設業界は、若手の人材不足が 長年にわたって課題とされており、特に社会全体の高齢化が著しい昨今では、より早急に解決しなければならない課題となっています。建設業が人材を集めにくい背景と して挙げられるのが、他業種に比べて賃金が低く、就労時間が長いという労働環境です。建設業は社会のインフラを支える非常に重要な業種であり、滞りなく社会を 動かしていくためには、働き手が集まりにくい現状からの改善を試みていかなければなりません。
法改正によって労働環境を改善し生産性を向上させることによって、 若い世代が建設業界への就職を望む環境づくりをしていくことが1つの目的とされています。
改正点①施工現場における労働者の処遇改善
1つ目の改正点は、主に賃金を引き上げることによる労働者の処遇改善です。法改正以降、建設業者には労働者が有する知識・技能などに基づき、公正な評価に沿った 適正な賃金を支払うことが労働者の処遇改善の努力義務として課せられます。
これはあくまで努力義務であり、明確なペナルティなどは存在しませんが、業界全体の 潮目を変える効果が期待されています。標準労務費の勧告という項目では中央建設業審議会に対し、労務費に関する基準を作成し、実施を勧告する権限が与えられました。 これにより労務費の適正化が図られ、賃金引上げに繋がっていくと考えられています。
また、著しく低い材料費等の見積りや原価割れ契約が禁じられ、違反した業者は 国土交通大臣または都道府県知事による勧告および 公表の対象となります。これによって労務費が圧迫されてしまうことを避けられ、賃金が下がってしまうことを 避ける効果が期待されているのです。
改正点②資材などの価格高騰による労務費へのしわ寄せ防止
2つ目の改正点は、資材などの価格高騰による労務費へのしわ寄せ防止です。受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化では、建設業者が工事を請け負う際、 資材の高騰などが予測される場合にそれを注文者へ通知しなければならないと定められました。この法改正によって、受注を獲得するために資材の高騰などの情報を 注文者に対して伏せ、労務費をコストカットすることで帳尻を合わせるといった形を避ける効果が期待されています。
また、請負代金の変更方法を契約書記載事項と して明確化するという改正も同様に、資材の価格高騰などに応じて、請負代金に速やかに反映することができるような法律となっています。そして、資材高騰時の 変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設では、資材の高騰などで協議が必要になった場合、注文者は誠実に協議に応じなければならないと義務付けられました。
一方的に注文者の立場が強くなることを避ける法律を設けることによって、労務費が圧迫されることを未然に防ぎ、労働者の処遇改善に繋がっていくことが期待されて います。特に近年は、世界情勢とも関連して資材などの高騰が著しいため、これらの法律が整えられたことによる労働者保護への意味は大きいと言えます。
改正点③働き方改革と生産性向上
3つ目の改正点は、労働時間の適正化・現場管理の効率化を軸に据えた、働き方改革と生産性向上です。受注者における著しく短い工期による契約締結の禁止という改正では、 工期ダンピングなどによる通常と比べて短い工期での契約を禁じることによって、労働環境の改善が図られています。また、従来の法律では重要な建設工事について 主任技術者・監理技術者を置くことが義務付けられていました。
対して改正された法律では、ICTの活用などを要件として、専任者の設置義務の緩和が図られており、 建設業者に対するコスト緩和効果が期待されています。公共工事発注者に対する施工体制台帳の提出義務を合理化という改正では、情報通信技術を利用する方法で 施工体制を確認できる場合、施工体制台帳の提出義務が免除されました。
他にも、効率的な現場管理の努力義務化・国による現場管理の指針作成という項目では、 特定建設業者は施工に必要な情報通信技術の活用について、必要な措置を講じるよう定められました。総じてデジタルトランスフォーメーションとも関連した 情報通信技術の活用を含めた合理化・効率化が図られた内容となっており、働き方改革と生産性向上に向けた効果が期待されています。
事業者が建設業法の改正前に準備すべきこと
今回は、2025年に予定されている建設業法の改正についてご紹介しました。全体的な傾向として、労働環境の改善が図られているのと同時に、注文者に対する 建設業者の立場を強めるような改正内容も多く見受けられたのが特徴です。法改正に則って対応を行うことは、業者にとっては負担に感じられるかもしれませんが、 施工品質の向上やスタッフの働きやすさに繋がると言えます。
そして、法改正に上手く対応していくためには、3つ目の改正点において中心に取り上げた情報通信技術の 活用が重要なポイントとなります。デジタル技術を積極的に活用し、業務全体を効率化していくことができれば、新たな法律にも適切に対応して労働環境を改善しつつ、 業績アップも目指せるでしょう。
#建設業法 #建設業